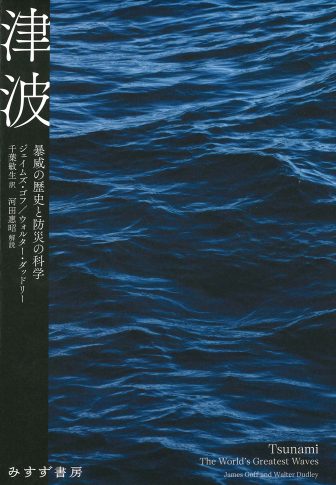おすすめ書籍第二十七回
- 2025年6月13日
- 本の紹介者: 鴫原良典(防衛大学校)
書籍情報
- 書籍 津波 暴威の歴史と防災の科学
- 著者 ジェイムズ・ゴフ,ウォルター・ダッドリー(著)千葉敏生(訳),河田惠昭(解説)
- 出版社 みすず書房,354頁
- 出版年 2023年
- 図書番号 978-4-622-09622-1
紹介記事
「Tsunami(津波)」という言葉が世界で広く知られるようになったのは,実はそれほど昔のことではありません.筆者が学生だった2000年代初頭,海外で「Tsunami」と言っても通じず,「地震によって起こるTidal Waveのようなもの」と説明して,ようやく理解されるという経験がありました.その状況を大きく変えたのが,2004年のスマトラ島沖地震・インド洋津波です.20万人以上の命を奪ったこの未曽有の災害は,津波の脅威を世界に強く印象づけ,「Tsunami」という言葉が国際的な共通語として定着するきっかけとなりました.
日本では,2011年の東北地方太平洋沖地震津波が,津波に対する認識を根本から変える契機となりました.この災害は,海岸防災や減災対策の見直しを迫り,海岸工学の分野にも大きな影響を与えました.
本書『津波――暴威の歴史と防災の科学』は,こうした近年の津波災害だけでなく,津波という現象を長い歴史と多様な起因を持つものとして捉え,世界的な視点から描いています.著者のジェイムズ・ゴフ氏とウォルター・ダッドリー氏は,津波堆積物の調査や災害教育の実践を通じて,各地で津波と人間社会の関わりを記録してきた研究者です.
紹介されている津波事例は実に多彩です.たとえば,約8,000年前に北大西洋で発生したストレッガー海底地すべり津波や,1958年にアラスカ・リツヤ湾で最大遡上高524メートルを記録した地すべり津波など,地震以外の要因で発生した津波がいかに巨大で予測困難であるかが示されています.
アメリカにおける津波の被害についても,本書では詳しく取り上げられています.近年では津波による被害が少ないため,日本ではあまり知られていないかもしれませんが,アメリカも過去に深刻な津波災害を何度も経験しています.1946年のアリューシャン地震津波や1964年のアラスカ地震津波など,20世紀中頃にはアメリカ本土やハワイ沿岸で繰り返し大きな被害が発生しており,とくに太平洋の中央に位置するハワイは幾度となく津波に襲われてきました.これらの災害が契機となり,太平洋津波警報センター(PTWC)が設立され,現在の国際的な津波警報体制の礎が築かれたことも紹介されています.また,1960年のチリ地震(Mw9.5)に伴う津波についても,その規模と広範な影響から,特に詳しい解説が加えられています.
日本の津波災害についても,幅広く丁寧に記述されています.1854年の安政南海地震津波と「稲むらの火」の逸話をはじめ,1944年の東南海地震津波,1946年の南海地震津波,そして2011年の東日本大震災に至るまで,多くの歴史的事例が海外の視点から紹介されており,日本における津波の記憶が世界の津波史の中でどのように位置づけられるのかを考える手がかりとなります.
本書には,こうした科学的・歴史的な内容に加えて,ユニークな話題も盛り込まれています.たとえば,第9章「世にも不思議な本当の話」では,津波の定義からは少し外れるものの,実際に被害をもたらしたアルコール津波や糖蜜津波といった興味深い事例が紹介されています.肩の力を抜いて読める章であり,津波という言葉の広がりや,比喩的な意味合いについて考えるきっかけにもなるでしょう.ぜひ本を手に取って確かめてみてください.
訳者による脚注や補足も丁寧で,日本の読者にとって読みやすい構成となっています.巻末には,京都大学名誉教授であり関西大学の河田惠昭先生による解説が収録されており,日本における防災研究や実践の視点から本書をより深く読み解く手助けとなっています.
津波防災に携わる専門家はもちろん,自然災害やその歴史に関心のある方にとっても,本書は「津波という現象」を多角的に学ぶことができる貴重な一冊です.災害に備えるうえで,私たちが過去の出来事から得られる教訓の大切さに改めて気づかせてくれることでしょう.ぜひ一度,手に取ってみてはいかがでしょうか.